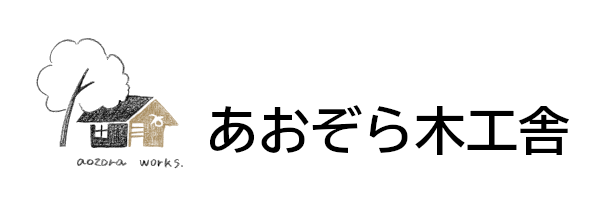風車を作り始めた訳(わけ)
きっかけは、当時の日本を根底から揺さぶった、あの出来事、東日本大震災でした。
もう、10年も経つんですね。
続く原発事故も、「ひょっとしたら、日本は終わり?」って思わせられる位、重苦しい状況を作り出しました。計画停電もありましたよね。
それらの記憶も風化しているんでしょうか……
一連の出来事で、再生可能エネルギーが脚光を浴び、あちこちで太陽光パネルを見かけるようにもなりました。そういう風に、自然に優しいエネルギーを積極的に利用すること自体は、きっと、良い事なんだと思います。
でも、どこかで割り切れないものも感じていました。
火力発電は炭酸ガスを排出するから原発の方が良い。でも、放射能が危険だから太陽光、風力、地熱…
でも、太陽光だって屋根の上に設置するなら、多分、問題ないと思うけど、山を切り崩して沢山のパネルを並べているのを見ると、「これってどうなの?」って感じてしまいます。風力や地熱だって、やり過ぎればおかしなことになるだろうし。
エネルギー使い放題の生活。足りなきゃ、違う場所から持って来ればっていう価値観じゃ、どうしたって行き詰るよなぁ…。って感じたのが風車づくりのきっかけでした。

(真ん中にある背の高い風車が初めて作った作品です。
今でも工房の看板として使っています。)
でも、初めのころは木の風車を作ろうなんて考えてなくて、誰でも思いつくような、風力発電機を作ってみようと思ったんです。
カッターで切ったペットボトルを風車の形にして、小さな発電モータを回してみたところ、発電はするものの、縁側で外の風に一日晒しても、その発電量は小さなLEDを一晩、点灯させるのがやっとという弱々しいものでした。
この結果から家庭用の電力を風力で賄おうとしたら、とんでもないことになるのは容易に想像できました。再生可能エネルギーといえば聞こえは良いですが、厳しい現実を目の当たりにして、考え方を変えざるを得ませんでした。
もっといい知恵はないものだろうか...
そして、手段が限られていた昔の人たちはどうやって涼を作り出していたのかと考えるようになります。
風鈴を軒先につるして、音色を楽しんでいる方は、今でも多くいらっしゃいます。
竹の虫篭に鈴虫を入れて、その鳴き声を楽しむなんて言うのも、いかにも日本の夏っていう感じでですね。
今の都会では実現しにくいかもしれませんが。
でも、こういったものに日本人の原風景といっても良いような郷愁というか、憧れに近いものを感じてしまいます。
こういうやり方で昔の人たちは暑い夏を乗り切ってきたんです。
直接的ではないけれど、人の感性に訴えかける素敵な工夫...
同じように感性に訴えかける方法で涼を演出する方法がないだろうかと考えるようになりました。
そして、風鈴の音や虫の声といった聴覚で出来るんなら、視覚でも行けるだろう、と思って作ってみたのが、木の風車でした。

(販売第一号の風車)
作ってみたら、思ったより好評で、多くの方々から関心をお寄せいただきました。
窓際に置いておくと、飽きずに眺めている自分に気付く事がよくあります。ほんのわずかな風でも、その存在を意識する事で、何となく涼しく感じる事が出来るようです。
今では、弊工房の看板商品の一つとなりました。
作り始めのころは拙いものでしたが、今ではそれなりに完成度も上がってきて、クラフト作品といっても恥ずかしくないものに成長したと思っています。
アイデアは沢山あるので、これからも様々な形の風車を作って皆様に楽しんでいただけたらと願っています。