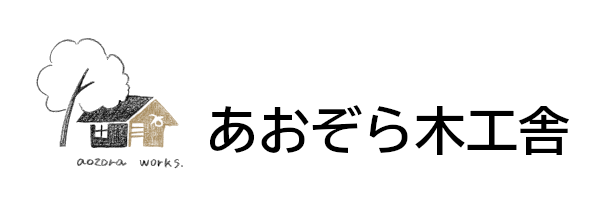風見鶏のある風車
風見鶏という言い方が正しいのかよく分かりませんが、要するに回転翼の反対側に尾翼が付いていて、風の吹いてくる方向に向きが変わるタイプの風車のことです。
初めて木の風車を作ろうと思った時、どういう形にしたら良いのか考えがまとまらず、相当、悩みました。
普通、風車と言われてイメージするのは大型の風力発電機や、オランダ風車ではないかと思います。
自分も、最初に連想したのはそれでした。
でも、
発電風車は何か無機的で引かれるものがない…
オランダ風車は風情はあるけどカタマリ感があってスタイリッシュじゃない…
…と、どちらもモチーフにするには気乗りするものではありませんでした。
その後、何かいいヒントはないかと、ネットをひと月も探し回ったでしょうか…
ある時、古くて朽ち果てたようなインデアン風車の画像を見つけた時、
「これだ!」
と感じました。(10年以上前のことで、何処のサイトかも忘れてしまいましたが…)
インデアン風車の基本的な形は、
・大きな回転トルク得るために多翼型であること(半面、回転数は遅い)
・風見鶏となる、尾翼が付いていること
・鉄塔のようなタワーの上に設置されること
と言えるかと思います。これらの特徴は、観賞用の作品にする場合にも有利で、
・多翼型(高トルク)であるという事は微風にも反応しやすい
(回転翼の枚数が多い方が、見た目にも美しいと思う。)
・単純な支柱より、タワーの方がカッコいい
そんな風に考えました。
そして作ったのが、これ↓

記念すべき1作目。典型的なインデアン風車。今でも工房の看板です。
その後、幾つかのタイプを作ってきましたが、販売の第一号は、これ。

回転翼に寄木の手法を使ってアクセントを入れています。
回転翼の白い部分はヒノキ、ストライプがブラックウォールナットです。
この風車、デザイン的にどうかなと思うところはあるのですが意外と人気があって、時々、再販の依頼やら注文が入ります。
その次に作ったのが、これ

回転翼と尾翼にブラックウォールナットを使ってアクセントにしています。

さらに、これ。

もともと、インデアン風車がデフォルメされて、少しずつ形が変わってきています。
この作品は、iichiで初めて特集に載せてもらった、記念すべきものとなりました。
同型を5点ほど作ったのですが、すべて手元を離れています。
他にも、幾つか作品はあるのですが、最新作はこれ。

木の風車・ハードメイプル

木の風車・ブラックウォールナット(同型)
ハードメイプルという木は北米産の楓の仲間です。
ブラックウォールナットも北米産でクルミの仲間。
日本の代表的な楓の仲間である板谷楓(イタヤカエデ)と比べると、木目は大人しいですね。
楓は栃と並んで白っぽい木の代表選手だと思います。
あっさりとはしていますが、その分、品が良く感じます。
このタイプの風車のデザインには、ずっと悩まされてきましたが、試作を重ねる中で、ようやく、そこそこ満足できると思える形が見えてきました。
台座も、これまでの丸く切った板から円環の形に変えました。両端を45度に切った4枚の板を張り合わせて、中空の四角を作り、これを旋盤で丸く削って円環にします。強度を増すために実(さね、かんざしとも言います)として色違いの木を入れてあります。こうしないと、接着面が剝がれてしまうことがありますので。
風車のデザイン上の肝は、平面を作らないことだと思っています。
大きな面があると、どうしても暑苦しく感じてしまいます。
涼しさを演出するためには空気感が大切だと思います。そのために、線で組み立てられた構造が良いと感じています。

支柱が3本だと角度によって不安定に見えるので、次回作で4本に変更します。


台座の脚には真鍮を使っています。木材でも良いような気もしますが、転倒防止のために重量を稼ぎたいのと、見た目の高級感を演出したいがための選択です。
ちなみに真鍮は有害物質である鉛を含まない材料(C6932B)を使っています。
一般的な快削黄銅(C3604)に対して、入手性が悪く高価なのですが、こういう作品には必要な配慮だと思っています。